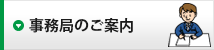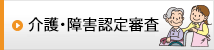日常生活に便利さや快適さをもたらす「火」も、ちょっとした不注意で火災の原因となってしまいます。
火災の知識
火災とは?
「人の意図に反して発生し、もしくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、もしくは拡大した爆発現象」と定義されています。

燃焼現象はなぜ起こるのか?
燃焼とは、「熱と光の発生を伴う激しい連鎖的な酸化反応」のことで、物質と酸素が結びつくことを「酸化」、熱と光が発生する「酸化」を「燃焼」と呼びます。
また、燃焼には必要な三要素があります。
- 可燃物(可燃性物質)
- 酸素供給源(支燃物)
- 点火源(熱源)
煙の恐ろしさ
火災等の災害に直面し、生命の危険がおびやかされるような状況下では、不安や恐怖等によって理性的な思考がなくなり、本能や感情等に基づく行動があらわれ、危険から逃避しようとして衝動的な行為に走りがちになります。
煙の階段の上昇速度は3~5m/秒、横方向への速度は0.5m~1m/秒の速さで広がります。
最初は火点がよく見えていても、燃えている場所を離れるにつれ、煙は冷却され急激に下降しますので、視界がきくうちに避難しましょう。



バックドラフト現象
気密性の高い構造の室内で出火した火災の場合、空気不足による不完全燃焼で燃焼が緩慢になりますが、このとき不用意に開口部を開けると急激に空気が流入し、爆発的に燃えます。
これを「バックドラフト現象」といいます。炎で火傷することがありますので、注意して下さい。

フラッシュ・オーバー現象
出火から最盛期にかけては、火災室内の可燃物が燃焼し、その燃焼により窓ガラスが焼け落ち、これによって空気の流通口が確保され、一気に燃え広がります。これを「フラッシュ・オーバー現象」といいます。
これを境にして火災室は大変危険な状態になりますので、大切な物を取りに戻ろうとしてはいけません。
防火の知識
火災を未然に防ぐために、みんなが「火」に対する正しい取り扱いを身に付けましょう。
たばこ
たばこの火の先端は700~800℃と非常に高温で、衣類などに火をつけるだけのエネルギーをもっています。たばこを吸うときは喫煙マナーを守り、喫煙後の消火を確認する習慣を身につけましょう。
たばこの火はすぐに燃え広がらない場合が多く、外出や就寝後に出火するケースがあります。中には、たばこの火が燃え移ってから数時間経過した後に出火したという事例もあります。 布団などにたばこの火が燃え移った場合、充分に水を含ませ、必ず消火の確認をしましょう。
防火のポイント
- 寝たばこは絶対にしない。
- 灰皿には水を入れ、必ず灰皿のあるところで吸う。また、灰皿に吸い殻をためないようにする。
- 完全に消えていない吸い殻はくずかごに捨てない。
こんろ(ガス・IH)
こんろの火をつけたままにしてその場を離れると、火災につながる危険がありますので必ず火を消す習慣を身につけましょう。温度の異常を感知し自動停止するこんろなどもありますが、こういった安全装置を過信しすぎないようにしましょう。
また、こんろと壁の距離が近すぎると壁板の内部に熱がこもり、壁材が徐々に炭化して火災につながることもあります。調理器具と壁板には適正な距離を保ちましょう。
こんろから炎が!してはいけない消火方法!
油を使った調理で鍋やフライパンから炎が出たときは絶対に水で消火をしてはいけません。 水をかけると炎は一気に拡大するので大変危険です。
防火のポイント
- こんろから離れるときは、必ず火を消す。
- こんろまわりは常に整理整頓しておく。
- こんろ・グリルは定期的に清掃し、油かすをためないようにする。
- こんろを使うときは衣服への着火に気をつける。
ストーブ(石油・ガス・電気)
ストーブは、使う人のちょっとした気の緩みや不注意から火災になることがあります。取り扱いや設置場所、給油方法にも十分に注意が必要となります。
こんなことをしていませんか?危険です!
- ○ ストーブの上に洗濯物を干している。
- ○ 火をつけたまま給油している。
- ○ ストーブのそばにカーテンや家具がある。
- ○ 火をつけたままストーブを移動させる。
防火のポイント
- 燃えやすいものの近くや、物が接触・落下するおそれのあるところでは使用しない。
- 外出時、退出時には必ずストーブを消す。
- 給油や持ち運びは火が完全に消えてから行う。
- 給油は灯油であることを確認する。絶対にガソリンは給油しない。
放火
放火は常に出火原因の上位を占めています。放火は深夜、人目を避けて無作為・発作的に行われるため、普段から放火されない環境づくりが大切です。
防火のポイント
- 家の周りに燃えやすいものを置かない。
- 物置、車庫などには鍵をかけ、外出時や就寝時には戸締まりを必ず確認する。
火遊び
何気なく机の上においたライターはありませんか?
子どもは好奇心が強く、火に対しても例外ではありません。注意をはらって火遊びができない環境を作ることが大切です。
防火のポイント
- 子どもに火の恐さ、正しい火の取り扱い方を教える。
- 子どもの手の届くところにマッチやライターを置かない。
- 子どもだけで花火などはさせない。
- 花火などで遊ぶ時は水バケツを用意するなど消火の準備を忘れない。
電気器具
日常生活に便利な電気器具も、ちょっとした不注意から火災を引き起こします。コードや電気器具に接続されたコンセント部分から出火するケースが多いため注意が必要です。
コンセント周りや配線にご注意!火事につながります!
- 配線を束ねて使っている:
- 熱が放散されずにたまり、使用を続けるとコードの被覆が溶けるほどの温度になります。
- 配線の一部が切れている:
- 一部切れた状態で使用していると、切れている部分に負荷がかかるため発熱します。
- たこ足配線をしている:
- 多数の電気器具で決められた容量以上を消費しようとするとコードなどに負荷がかかり発熱します。
- 配線が折れている:
- 一部分に圧力がかかり、1本のコード芯線同士が接触するとショートし火花がでて危険です。
- 接続部にほこりがたまっている:
- コンセントとプラグとの隙間に溜まったほこりが湿気を含むことで電気が流れて発熱します。
防火のポイント
- 電気のコードをカーペットや家具の下敷きにしない。
- 壊れたコード(被覆が破れているなど)を使用しない。
- 家具類などに隠れているコンセントは、ほこりをためないように定期的にチェックをする。
- コードを束ねて使用しない。
- たこ足配線はしない。
- 電気器具の使用後はプラグを抜く
消火と避難
消火
火事が起きたら迷わず消火器を使いましょう。
なお、天井に炎がとどく、又は天井に燃え移った時点で、消火器による初期消火はできないと判断してください。
速やかに初期消火を中止し、避難してください。

避難
火事で一番危険なのは煙です。
消火に失敗した場合は火元の部屋の扉や窓を閉めてから避難してください。扉や窓を開けたままにしておくと、空気が流れ込むことによる燃焼の助長に加え、避難する廊下や階段に短時間で煙が充満してしまう原因となります。
立った状態での避難は煙を吸ってしまいますので、身を低くして避難してください。また、ハンカチやタオルがあれば水で濡らして鼻や口に当て熱い煙を吸い込まないようにして避難しましょう。
また、室内に忘れ物等を取りに戻ることは非常に危険です。煙と炎で身動きがとれなくなるかもしれませんので、一度逃げたら絶対に引き返さないようにしましょう。